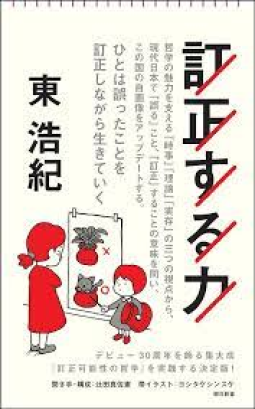
訂正する力
朝日新書
東浩紀
この作品は、現在アーカイブされています。
ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。
出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。
1
KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
2
Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。
刊行日 2023/10/13 | 掲載終了日 2024/04/08
ハッシュタグ:#訂正する力 #NetGalleyJP
内容紹介
ひとは誤ったことを訂正しながら生きていく。
哲学の魅力を支える「時事」「理論」「実存」の三つの視点から、
現代日本で「誤る」こと、「訂正」することの意味を問い、
この国の自画像をアップデートする。
デビュー30周年を飾る集大成『訂正可能性の哲学』を実践する決定版!
聞き手・構成/辻田真佐憲 帯イラスト/ヨシタケシンスケ
保守とリベラルの対話、成熟した国のありかたや
老いの肯定、さらにはビジネスにおける組織論、
日本の思想や歴史理解にも役立つ、隠れた力を解き明かす。
それは過去との一貫性を主張しながら、実際には過去の解釈を変え、
現実に合わせて変化する力――過去と現在をつなげる力です。
持続する力であり、聞く力であり、記憶する力であり、
読み替える力であり、「正しさ」を変えていく力でもあります。
そして、分断とAIの時代にこそ、
ひとが固有の「生」を肯定的に生きるために必要な力でもあるのです。
(目次)
第1章 なぜ「訂正する力」は必要か
第2章 「じつは……だった」のダイナミズム
第3章 親密な公共圏をつくる
第4章 「喧騒のある国」を取り戻す
日本には、まさにこの変化=訂正を嫌う文化があります。政治家は謝りません。官僚もまちがいを認めません。いちど決めた計画は変更しません。(…)とくにネットではこの傾向が顕著です。かつての自分の意見とわずかでも異なる意見を述べると、「以前の発言と矛盾する」と指摘され、集中砲火を浴びて炎上する。そういう事件が日常的に起きています。(…)そのような状況を根底から変える必要があります。そのための第一歩として必要なのが、まちがいを認めて改めるという「訂正する力」を取り戻すことです。(「はじめに」より)
おすすめコメント
★超話題の新書!期間限定で公開中です★
★超話題の新書!期間限定で公開中です★
販促プラン
★読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューを投稿ください!
著者・担当編集ともに楽しみにお待ちしております。
投稿いただいたコメント・感想の一部は、弊社HP、SNSにて公開させていただく可能性がございます。
また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。
ご協力の程、何卒宜しくお願い致します。
★★★★★
作品の拡材やご注文をご希望の書店様は
恐れ入りますが<朝日新聞出版販売部>まで直接お問合せをお願い致します
【NetGalley 会員向け企画】
「注目のビジネス書にレビューを書こうキャンペーン」
NetGalleyに掲載中のビジネス書グランプリ2024 エントリー作品にレビューをご投稿いただいた方の中から抽選で20 名様に図書カードネットギフト1000 円分をプレゼント!
★レビュー投稿締め切り:2024年1月31日まで
・応募期間終了後、当選者へはメールにてご連絡いたします。NetGalley登録アドレスを出版社へ開示している方が対象となります。
・当選の発表はメール通知をもってかえさせていただきます。
出版情報
| 発行形態 | 文庫・新書 |
| ISBN | 9784022952387 |
| 本体価格 | ¥850 (JPY) |
| ページ数 | 256 |
関連リンク
閲覧オプション
NetGalley会員レビュー
 レビュアー 530109
レビュアー 530109
『日本には、まさにこの変化=訂正を嫌う文化があります。政治家は謝りません。官僚もまちがいを認めません。いちど決めた計画は変更しません。誤る(あやまる)と謝る(あやまる)はもともと同じ言葉です。今の日本人は、誤りを認めないので謝ることもしないわけです。』
どんなことを問いただされても「検討します」「善処します」しか言わない政治家。不祥事があって頭は下げるけど具体的な対策ができない経営者。あの人たちはそうやって時間が過ぎるのを待とうとしているだけなのだなと思うと、実に情けなくなってきます。間違ったら、どこが問題なのか考え、直していくということって当り前じゃないんですか!誤ると謝るは同じなんですよ!って叫びたくなることが多過ぎます。
『人は老います。人生は交換できません。それゆえ、ある時点からは訂正する力をうまく使わないと生きることがたいへん不自由になります。』
たとえば歳を取ると老眼になります。老眼鏡を掛ければいいだけなのに、なぜかそれを嫌がる人っていますよね。若い頃ほどたくさん食べられなくなるし、寝つきも悪くなるし、なのに頑なに自分は若いと言張り、嫌われる中高年ってなんだか悲しいです。そんな風に意固地になるということ自体が「老い」だって気づかないのかなぁ。
そうか、歳を取るということはこういうことなのだなと素直に受け止め、自分が生きやすいように生活を変えていけばいいだけなのにねぇ。
それは人も社会も同じこと。訂正しながら世界の流れに乗っていくって、そんなに難しいことなのでしょうか。
 レビュアー 781279
レビュアー 781279
ゲンロンは好きな作家さんの番組を単発で購入して視聴するときがある。その番組のCMで話されているのが著者である東浩紀さんであることは知っていたが、恥ずかしながら初めて著書を読んだ。
「訂正する力」とは一体何だろうか。
なぜ今日本に「訂正する力」が必要とされているのだろうか。
時事問題や具体的な名前を挙げて、日本人が「訂正」を嫌うということが書かれている。特にネットでこの傾向が顕著だとも。
確かに、ある意見に対して大きな声を擁護する発信は多くなる。しかしその意見が間違っていたり、変化したとしても議論の余地もなく盲信してしまう人たちもいる。
今正しいとされていることが数年後には見解が変わることなどたくさんある。その時私たちはその考えを「訂正」していく力が求められている。
第2章で語られるように、私たちは日常的に過去を訂正しながら生きている。そのとき「じつは‥‥‥だった」という要素を加えると物事が変化するという事例に納得した。
「訂正する力」を高めるのにはもっと物事を多角的に見る必要がある。そして他者との対話や、知識がその基礎となる。
この本は書店で最近よく見かけて気になった。
最近はこういう思想的な本や哲学書を読まなくなっていた。年齢を重ねて自分の考えが凝り固まっていたのかもしれない。
まさに私こそが「訂正する力」が足りていない、そう気付けたのはこの本のおかげである。
 レビュアー 981507
レビュアー 981507
政治、歴史、経済と幅広い視点で著者の考えが述べられていて、
「考える力」の必要性を問き、「訂正する力」というテーマにつながっていきます。
「コスパ」と「タイパ」の世の中で私自身も戸惑うことが多々ありますが、本書には経験する場、話していい場など好転させるヒントが多々ありました。
時代が急激に変化する世の中であっても、著者が述べられたように、「自分はこれでいくという決断力と、批判を受け入れる力」を持ち合わせる人になりたいと強く感じた1冊です。
 レビュアー 1025593
レビュアー 1025593
人は誤りを認めたがらないもの。
言い訳したりばっさりとリセットしたり、時には排除することも。
けれど、ぶれないことに固執せず、柔軟に訂正して生きていこう。
子供たちの遊びのように、ルールが変わってもゲームが続いていると思わせる力が平和につながる!
【訂正する力】
#東浩紀 #.朝日新書 #ヨシタケシンスケ
今、日本に必要なのは訂正する力である。
大胆な改革が必要であるが、実際には何もすすまない日本の現状。
間違えを認めて直すという
#訂正する力 がいま必要。
リセットすることとぶらないことの間を意味する。
◯ヨーロッパの人は訂正する力が強い
◯ロックダウンしたと思えば、収束すればマスクを外していく
◯訂正する力がないと生きることが不自由になる
日本のことを考えている内容でした。
時代遅れの規則やルールは変化させ、訂正していく。
それが、いまの日本に必要なことだとわかりました。
.
.
.
.
#訂正する力
#訂正
#憲法 #lgbt #政治 #日本
#読書
#読書日記
#読書ノート
#読書記録
#読書習慣
 レビュアー 545935
レビュアー 545935
最近の普通の日本人は品行方正である。幅員5m程度の車道で、車の姿がなくても赤信号をじっと待つ。赤信号皆で渡れば怖くないはどこに行ったのか。
思考の停止状態なのである。そして「いつのまにか変わる」ことを待っている。
ルールがなんのためにあるかを考えない。ルールは自分が生きるためにあるのである。しかし人間は一人では生きていないのである。自分のルールとはちがう他人のルールがある。ふたつのルールはどちらが正しいというわけではないので訂正せねばならぬのである。しかも喧嘩をするわけにもいかないので喧々諤々と話しているうちに「いつのまにか」訂正されているのである。喧々諤々がないと「いつのまにか」訂正されることはないのである。待っているのはダメである。自分たちで喧々諤々しなくてはいけないのである。





