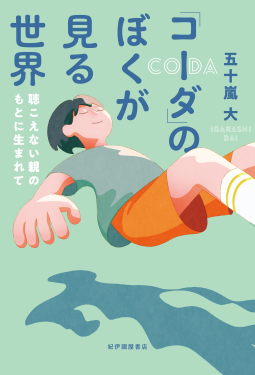
「コーダ」のぼくが見る世界
聴こえない親のもとに生まれて
五十嵐大
この作品は、現在アーカイブされています。
ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。
出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。
1
KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
2
Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。
刊行日 2024/08/02 | 掲載終了日 2025/05/31
ハッシュタグ:#コーダのぼくが見る世界 #NetGalleyJP
内容紹介
第71回青少年読書感想文全国コンクール
課題図書 高等学校の部
もしも、親の耳が聴こえたら――なんて、想像もつかなかった。
ときに手話を母語とし、ときにヤングケアラーと見なされて……
ろう者と聴者のはざまで生きる〈コーダ〉の経験を通じ、言語やコミュニケーションの大切さ、自分と異なる人の立場を想像する難しさを知るノンフィクション。
映画「ぼくが生きてる、ふたつの世界」原作者の最新刊!
※コーダ(CODA)=Children of Deaf Adultsの略で、聴こえない/聴こえにくい親のもとで育つ、聴こえる子ども。
「あなたはコーダなんだね」と言われたとき、生まれて初めて感じるような衝撃を受けた。自分のような生い立ちを持つ者を総称する言葉がある。その事実は、たしかな安堵をもたらした。名前が付けられるということは、同じ境遇にある人が一定数以上存在することを意味するだろう。つまり、ぼくはひとりではないということだ。(本文より)
おすすめコメント
第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部)に選定されました。5月30日(金)までにレビューをお寄せください。
第71回青少年読書感想文全国コンクール課題図書(高等学校の部)に選定されました。5月30日(金)までにレビューをお寄せください。
出版情報
| ISBN | 9784314012089 |
| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |
| ページ数 | 176 |
閲覧オプション
NetGalley会員レビュー
 図書館関係者 612127
図書館関係者 612127
最近やっと名前が知られてきた「コーダ」。「大変」とかつい思ってしまうけど、周囲に言われる前はそれが当たり前なんだよな。
わかっているのに、そう言われるとやっぱり偏見があるのかな。と思ってしまう。そして、手話と日本語の文法がまったく違うというのも
驚き。歌に手話をつけるって聞こえる人の自己満足でしかないのかも。とか書いてやりとりできればそれで十分意思疎通ができている、
と思うのは聞こえる人側だけの満足だったかも。とかグルグル考えた。
 レビュアー 912561
レビュアー 912561
『ぼくが生きてる、ふたつの世界』
『聴こえない母に訊きにいく』
の五十嵐大氏の本がYA向けに出版されたと知り、子どもたちに読んでみてほしくてリクエストさせていただきました。
『コーダあいのうた』
『デフ・ヴォイス─法廷の手話手話通訳士』
『しずかちゃんとパパ』
など、コーダやろう者が登場する映画やドラマについてや、作品についての著者の見解も言及されていて興味深く読みました。
ここ数年で認知が進んできたコーダの問題はともかく、ろう者やろう文化については、
「知ってもらうという段階はとうに過ぎている」
という指摘にハッとしました。
このような作品を通してろう者やろう文化を意識するきっかけになった私には、ろうの方の直面されている問題は「新しく知った」問題だが、当事者の方たちにとってはずっと昔からそこにあって、今なお解決されない日々の「困りごと」なのですね…
手話についての認識ひとつとっても当事者の方とそうでない人たちの間には誤解があり、その原因は当事者でない側の知識、認識不足があること、それなのにマイノリティとされる人々について、マジョリティがマジョリティの価値観で判断する「当事者不在」の議論が続いているという現実は依然としてあることを再認識し、自分も「当事者不在」の思考を繰り広げていないか、たとえばマイノリティの方について取り上げた作品を娯楽として消費していないかなど、総点検が止まりませんでした。
また
「この社会はあまりにも”健常であること”を前提として作られている」
という点にも頷くほかなかったです。若い頃は認識していなかったが、妊娠、出産、子育てを通して、世の中は「妊婦」や「子連れ」が気軽に出歩けるような仕組みになっていないと知りました。
第71回青少年読書感想文全国コンクール高等学校の部の課題図書になっていたらしく、うちの子たちにはまだ少し難しいところもあるかと思いますが、購入しておきたい一冊です。
 レビュアー 946550
レビュアー 946550
聴こえない親を持つ「コーダ」としての経験を綴った作品。
著者は、手話を母語としながらも、聴者の世界にも属するという独特な立場にあり、日常の中で感じる葛藤や、社会との関わり方について深く考えさせられます。
手話と日本語の違い、コーダとしてのアイデンティティ、そしてマイノリティとして生きることの難しさが描かれていて、己の無知にあ然とします。
文章は読みやすく、著者の率直な語り口が心に響きます。コーダやろう者の世界について知るきっかけとなるだけでなく、社会の中で「理解すること」の大切さを改めて考えさせられる一冊です。
多様な視点を持つことの重要性を感じる、貴重な作品でした。
 図書館関係者 601014
図書館関係者 601014
気になりながら未読だった作品が掲載されていたのでこれを機に読んでみましたが、
コーダに限らず、「ラベル」があることのよい点も問題点も両方伝わる本でした。
どの分野においてもマイノリティの悩みを深めるのは「自分だけ」と思えてしまうことで、
だからこそ解決策なんてどこにもないように思えてしまいもするのだけれど、
「一人ではない」という気付きが得られやすいような世の中になるといいなと思います。
ただ個人的には公開時に見た『エール!』が好きだったので、
アカデミーを取った焼き直しばかり有名になったのが残念です。
フランス映画は見る人少ないから仕方ないかもしれませんが。
 図書館関係者 868527
図書館関係者 868527
読書感想文課題図書が発表されたタイミングでリクエストしました。おそらく「コーダ」という名称を初めて認識する生徒も多いかと思いながら、読みました。当事者の声には力があります。そして、憶測ではない事実があります。課題図書という事で押し付けにならず、生徒達には「そのままの声」が真っ直ぐに届くように読んで欲しいと思いました。
 レビュアー 1604179
レビュアー 1604179
聴こえない世界と聴こえる世界を行き来する子どもたち、コーダ(CODA)。ろう者の子。読書感想文課題図書を数冊読んだが、自身の視野の狭さを痛感。手話と字幕の併用の必要性、手話歌への気づきも与えてくれて、ソーダ(SODA)の会があることも知った。読書を続けていると、こういう見えていない世界を感じる機会を多々得られる。社会が変わっていく中で、自身が変化するには興味関心が必要。世間に発信される情報の表面だけでなく深掘ることで成長する。現状を知ることができれば、手と手を取り合える、受け入れられる社会に近づくだろう。
 レビュアー 1049450
レビュアー 1049450
「コーダ」という言葉は聞いたことがあった。
聴覚障がいのある両親のもとに生まれた聴者を指す言葉だということも理解していた。
言葉としては知っていても、それが実際にどういうことなのか、全くといっていいほど知識がなかった。
本書は、「こういう人がいますよ」「こういう風に暮らしていますよ」「差別はいけませんよ」「お互いに理解し合いましょうね」というような、単純なことが書かれているわけではない。
コーダである著者が、どういう環境の元、どういう気持ちで、どうやって今まで暮らしてきたのか。
きれいごとだけではない。
一人の人間が、理解されない苦しみ。
『コーダ』というラベルで一括りにされることで得た安心感と違和感。
そう言った本音や葛藤が赤裸々に語られている。
同じ「コーダ」であっても、人によって、それぞれ考え方が違う。
当たり前のことだ。
外国で、「日本人だから魚が好きだろう」と魚を振舞われても、魚が嫌いな日本人だっている。
それが、マジョリティの立場からは、理解が及ばない。
そういった、マイノリティーの置かれた状況、日々感じる不平等の世界を、著者が明確に言葉に表してくれた。
本書を当事者以外の人たちが読めば、知らない世界を知り、聴覚障がい者やコーダ、その他のマイノリティーに配慮しようと気持ちになると思う。
そういう意味では、もちろん良書だが、それ以上に、当事者たちが、自分たちの抱える、言い表せない気持ちを語化してくれたということに喜びや安ど感を覚えるのではないかと思う。
 教育関係者 751214
教育関係者 751214
昨年映画化された『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の原作者のエッセイ。
「コーダ」とは「耳の聴こえない、あるいは聴こえにくい親のもとで育った、聴こえる子どもたち」を意味するという。
この本でも紹介されている海外映画『コーダ あいのうた』の印象でコーダの人たちは「ヤングケアラー」の要素がかなりあると思っていました。その点については「ケア」とは、というところから作者は丁寧に説明してくれています。
「好きなのに嫌い」「嫌いなのに好き」という世の中には聴こえる親がいる、と知った時からの揺れる思い。
各家庭の事情と個人によるのでしょうが、そんな自分の心情についても書かれています。
ドラマなどでの手話の流行について、テクノロジーの進化についての記述はとても興味深かったです。
また聴覚に不自由なきょうだいがいる人のことを「SODA 」というのも、今回初めて知りました。
最近の課題図書では「多様性」がテーマになっていることが多いです。
LGBTQ、色覚障害がい、難聴…このような人たちを合わせたら、健常者優先社会がいかに生活しづらいものなのか想像できます。
高校生の課題図書ですが、中学生はもちろん小学生の高学年でも読めそうですし、読んで欲しい本でした。





