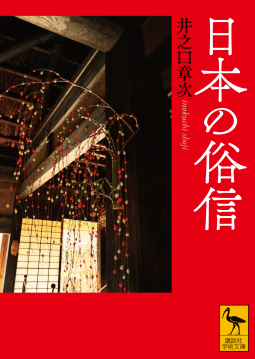
日本の俗信
井之口章次
この作品は、現在アーカイブされています。
ぜひ本作品をお好きな書店で注文、または購入してください。
出版社がKindle閲覧可に設定した作品は、KindleまたはKindleアプリで作品を読むことができます。
1
KindleまたはKindleアプリで作品を閲覧するには、あなたのAmazonアカウントにkindle@netgalley.comを認証させてください。Kindleでの閲覧方法については、こちらをご覧ください。
2
Amazonアカウントに登録されているKindleのメールアドレスを、こちらにご入力ください。
刊行日 2025/06/10 | 掲載終了日 2025/06/10
ハッシュタグ:#日本の俗信 #NetGalleyJP
内容紹介
\ 靴の紐が切れるとよくないことが起こる /
本当の理由、ご存知ですか?
■
「靴の紐が切れるとよくないことが起こる」
「他所で爪を切ってはならない」
「丙(ひのえ)午(うま)の年は出生数激減(次回は2026年!)」…etc
全国各地で採集された俗信、すなわち「超人間的な力の存在を信じ、それに対処する知識や技術」を、「予兆」「卜占」「禁忌」「呪術」「妖怪」「憑物」の項目別に分類し、体系的に捕捉。‟非科学的で取るに足らぬもの”とされた俗信から日本文化の基層を明らかにする、民俗学の精華。
[ 担当編集者より ]
現代のわれわれは、「靴の紐が切れるとよくないことが起こる」理由について、「普段の点検が悪いか、慌てていたのだろう。そんなときはえてしてよくないことが起こるものだ」と、‟科学的”に考えることができます。しかし、著者の井之口章次さんは、この俗信の由来はそんな教訓じみたものではないと言います。では、それは一体どうしてできあがったのか? キーワードは「連想」。本書を覗いて、気になる俗信の由来を確かめてみてください。
解説は、『ネット怪談の民俗学』の廣田龍平さんです。
■
内容の一部を抜粋でご紹介
貧乏ゆすりと呼ばれる無意識の行為がある。
○ 膝などを絶えず小刻みに動かすものではない。もしそういう行為をすると、貧乏になる。
というもので、禁を犯した場合の制裁(貧乏になる)が、名称の中に組み込まれているのである。貧乏ゆすりは貧乏人だけがするものではないし、貧乏人がみな貧乏ゆすりをするわけでもない。現代の世相の中では、ちょっと理解しにくくなっているが、明治・大正から昭和にかけて、都市的なものが徐々に発達し、村落共同体や家族制度からハミ出した人々が都市に集まってくる。しかし社会保障制度のほとんどなかった時代に、いわゆる中風になった気の毒な人々が生活に窮し、橋の袂や往来に坐って物乞いをすることが多かった。そういう光景を日常的に見聞している人々の間では、手足の震動と乞食、したがって貧乏とを、連想的に結びつけることは容易であった。貧乏ゆすりという言葉には、ユーモアさえ感じられるが、実はこのような残酷さを背負っているのである。
--------------------------------
著者/井之口章次(いのくち・しょうじ)
1924-2012年。兵庫県生まれ。國學院大學国文科卒業。専門は民俗学。民俗学研究所所員、杏林大学教授、日本民俗学会理事などを歴任。著書に『日本の葬式』『民俗学の方法』『伝承と創造』『生死の民俗』などがある。
解説/廣田龍平(ひろた・りゅうへい)
1983年生まれ。大東文化大学助教。専攻は文化人類学、民俗学。博士(文学)。著書に『妖怪の誕生』『〈怪奇的で不思議なもの〉の人類学』『ネット怪談の民俗学』、訳書にマイケル・ディラン・フォスター『日本妖怪考』がある。
出版社からの備考・コメント
空白ページは削除して公開しております。
発売前の大切なゲラをご提供させていただいております。弊社では、下記のような方からのリクエストをお待ちしております。
○発売に向けて、一緒に作品と著者を応援していただける方
○NetGalleyへレビューを書いてくださる方
○自分には合わない内容だった際、どういったところが合わなかったかなど、建設的なご意見をくださる方
下記に該当する方のリクエストはお断りさせていただく場合がございます。
ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
○お名前・所属などに詳細な記載がなく、プロフィールにてお人柄が伺えない方
○作品ごとに設けました外部サイトへのレビューのルールをお守りいただけない方
○フィードバック率の低い状態が長く続く方
※※リクエストの承認につきましては現在お時間をいただいております。
おすすめコメント
--------------------------
[ NetGalley担当者より ]
子どもの頃、親に「貧乏ゆすりやめなさい!」と言われ、理由もわからないまま「貧乏ゆすりは良くないこと」とぼんやり刷り込まれていた「言い伝え」や「習わし」の答えがここで見つかりました。
本書の原本は、1976年(昭和51年)に弘文堂より刊行されたものです。廣田龍平さんの解説によると、「理論的な関心は第一章と第二章で提示されており、それ以外の章は独立して読んでも楽しめるはずである。」とのこと。
目次から、または巻末の索引から、気になるキーワードがあるページを読んでみて、そこから前後の関連項目を読んでみるのも良いでしょう!
--------------------------
販促プラン
★
読み終わりましたら是非NetGalleyへレビューをご投稿ください!
著者・担当編集者ともに楽しみにお待ちしております。
また、適したメディアやお持ちのSNSにもレビューを投稿いただき、多くの方に本を拡げていただけますと嬉しく幸いです。
※発売前作品のため、ネタバレになるレビューはお控えくださいませ※
ご協力の程、何卒宜しくお願いいたします。
★★★
作品の拡材や指定配本をご希望の書店様は
恐れ入りますが<講談社 書籍営業部>まで直接お問合せをお願いいたします。
★★
出版情報
| ISBN | 9784065399569 |
| 本体価格 | ¥1,600 (JPY) |
| ページ数 | 384 |
閲覧オプション
NetGalley会員レビュー
 レビュアー 1582019
レビュアー 1582019
勉強になる・知識が増える一冊です!
写真も掲載されていて、資料・教科書って感じ。マーカー引いたり付箋を付けたりしたくなる。面白い!
大学の民俗学講座とかで教科書に採用されているイメージが湧きました。あと、ホラー好きな人、ホラー小説を書く人にすごく好かれそう。「これこれ、こういうの欲しかったんだよ!」って声が聞こえてくるようです。
写真とその下に添えられた短い解説を眺めていくだけでも楽しいし、論理的な本文をじっくりと読むのもとても気持ちいいです。知的な教授が語っているのを聞いている生徒の気分になれる。
さらっと呼んで終わりにするには惜しく思えて、自宅に置いておきたくなりました。価値のある文献、みたいな。
 レビュアー 1666318
レビュアー 1666318
とても読み応えのある本でした。日本の俗信について多数の実例を挙げながら、分かりやすく書いてありました。黒不浄、赤不浄、白不浄など初めて知る言葉もたくさんあり、夢中で読み進めました。特に、味噌と
「死」の関係は意外でした。現代社会においては、ナンセンスと片付けられてしまう事柄かもしれませんが、こうした本を読むことで、日本人の本質のようなものを探ることができると思います。
 レビュアー 1446986
レビュアー 1446986
思ったより古い本だったことは自分の確認が甘かった。でも面白いし分かりやすかった。一章の『俗信概論』だけで読み応えがあるし、知らないことばかり。良い夢の「一富士二鷹三茄子」は有名だけど「四葬式、五火事」ってどう考えても縁起悪そうなのに、って思ったらちゃんと解説してくれる。平易な文章と写真もふんだんに使って、講談社学術文庫はこういうのが良い。民俗学もっと色々読みたい。
 レビュアー 540565
レビュアー 540565
日本思念
日本思念、そんな言葉があるかないかわからないあが、これは記憶である。
つまり、俗信とは記憶の刷り込み。
見事なもので、デジタル化が進む現代でもその思念は根強い。
私は納棺師であったため、こういった世界観は大好物。
意味はあって、理由もあったが、確実ではない。
そんな、曖昧な根拠の世界観が大好物。
現代人に問う、風習はなぜ必要で行われているのか?
そこに見える、思いや願いが汲み取れたら、それは未来のだれかに紡ぐメッセージとなり得るだろう。
 教育関係者 454232
教育関係者 454232
あー今になってこういう講義とか受けてみたかったなと思う。
最近日本の子供たちがごんぎつねを読んで葬式の準備をしている村の女の人たちが死体を煮ているなんて真面目に話し合っているという記事を読み仰天した。私もごんぎつねを子供達に教えたことがあるけれど、その時はどうだったかななんて考えていたら、そういえば日本のお葬式についてフランスに住んでいる子供たちはほとんどの子が行ったことないだろうし、何ならフランスの葬儀も知らないと思ったので簡単に日本の葬儀、現在ではどんなことをするのかや、昔はどのように行なっていたのかを写真付きのプリントを作り教えているなと思った。
私もそういえば昔の葬儀についてはそこまで詳しく知らなかったし、棺桶の形も違っていたなど実際大人になってから知った気がする。なので、この本を読むと昔の風習や昔からの考え方などがわかり、子供達に文化を伝えていく上でも役に立ちそうだなと思いました。
例えば鼻緒が切れたら良くないことが起こるなど、へえ!そうだったのかと思ったこともたくさんありすごく興味深く拝読させていただきました。
 レビュアー 1074736
レビュアー 1074736
最後の第七章「死と俗信」が全384p中、かなりの部分を占める(実は既に何ページからか確認できない)。著者井之口章次のウィキペディアの項に、特に葬儀に関する民俗事例を多数研究発表しており、『仏教以前』(1954年)や『日本の葬式』(1965年)などの著書で知られる。葬儀を中心的な研究題材にしたのは「日本人の霊魂観」を知ることの出来る対象だからだとしている。また、俗信や妖怪についての研究も多く手掛けており、おもな論及は『日本の俗信』(1975年)にまとめられている、と書かれているのが本書。それを講談社学術文庫として刊行されたのが先月。よって「死」を扱った部分が面白かった。死に際し魂は善光寺に行き、帰ってから埋葬するという俗信があるそう(日本中)。聞いたことが無いなあ、と思っていたら、つまり「一生に一度は善光寺参り」ということで生前に行ったことは無い人は埋葬される前にあわてて魂になって行ってくるということだという。なんかキリスト教の「聖体拝領」(よく知らないのだが)を思わせる。仏教でいえば「成仏」ということだろう。こういった俗信を多く収録した本。そもそも民俗学者の著作であるから「研究書」であるのだが(つまり論理的な扱い)相手が「俗信」だけに解釈には、あまり学問的に思えない箇所もある。例えば「初七日」(通夜や四十九日も)の理由としてその間に生き返る可能性、つまり本当に「仏」になったのかの保留期間だというのは医学が発達していなかった昔は、「生き返る」ということは、さすがに7日後はなくとも、可能性は、ありそうだ。しかし喪に服する期間としての意味も含めて考えると、実は感染を避けた期間、つまり感染症による死が理解できなかった昔、親族等は蟄居し、感染の疑いが消える期間が初七日の意味という考えがあってもいいと思うのだが。昔は「死」は穢れ、だとされていた意味も感染とういう観点もあったのではないだろうか。さらに本書には「味噌」や「餅」また「塩」勿論、「枕飯」等、死者に関するものは親族、弔問者に供するものとは別に準備する(具体的には精米、洗米、炊飯等のこと)ことの意味も「感染」という観点から考えられる気がする。「忌中」を表示したのも要は隔離。なお関連して「殯(もがり)」がある。日本の古代に行われていた葬送儀礼。死者を埋葬するまでの長い期間、遺体を納棺して仮安置し、別れを惜しみ、死者の霊魂を畏れ、かつ慰め、死者の復活を願いつつも遺体の腐敗・白骨化などの物理的変化を確認することにより、死者の最終的な「死」を確認すること。その柩を安置する場所をも指すことがある。殯の期間に遺体を安置した建物を「殯宮」(「もがりのみや」、『万葉集』では「あらきのみや」)という(ウィキペディア)。現在では、天皇・皇后・太皇太后・皇太后の大喪儀の一つとして行われる(通夜は殯の簡略化というのが通説)。本書では「殯」の残滓が「喪屋」という形で残る例があるとしている。蛇足だが、そもそも墓という考え方は、古代には、あまり無かったのでは。「仏」(神道でいえば「神」)になってしまえば「あの世」に存在するわけだから「この世」には存在しないのであって供養のためなら位牌で済む。「両墓制」の参り墓(埋め墓とは別の場所にある、墓参するのはこちら)は別に家の敷地内でもいいわけだが集落が形成されると寺の境内に集中し現代の墓地になったらしい。





